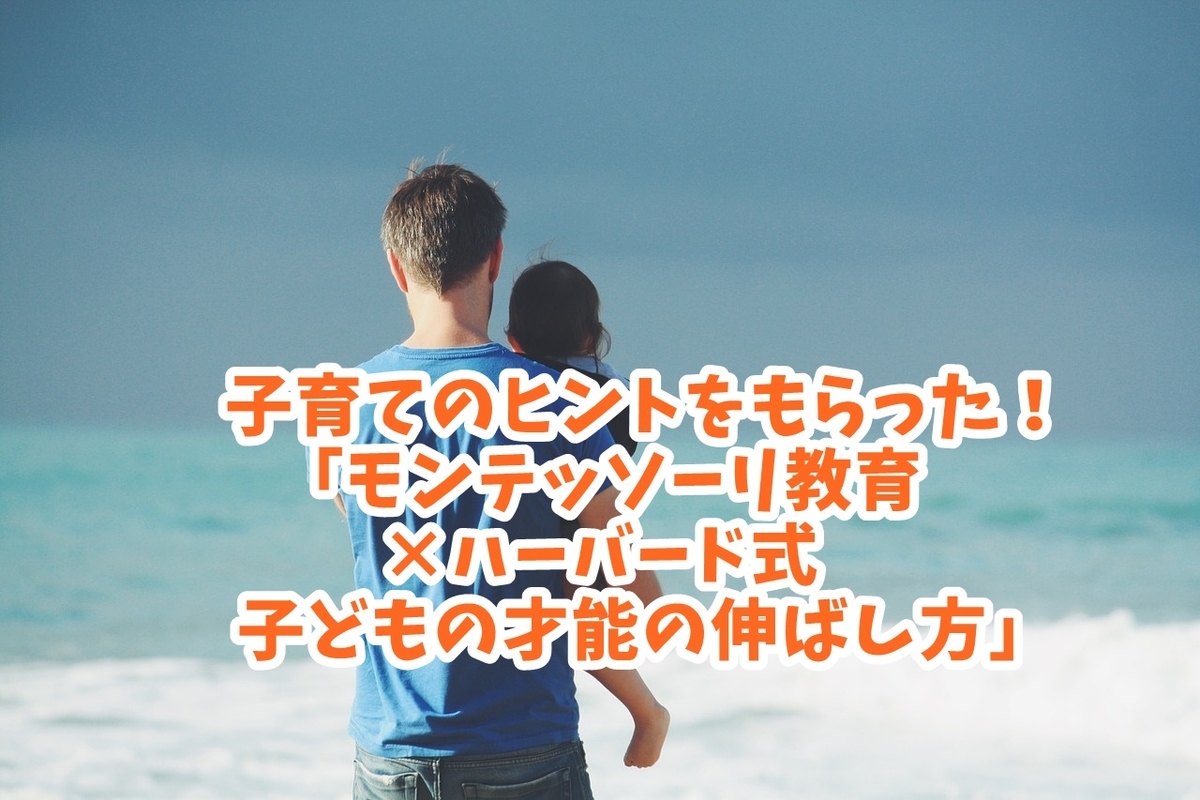
本書「子どもの才能の伸ばし方」は、「モンテッソーリ教育」と「ハーバード式」をミックスした内容となっています。
「モンテッソーリ教育」「ハーバード式」と聞くと、思い浮かべてしまうのは
特殊な教材やドリルをガリガリさせるようなイメージ
かもしれません。
でも、全然違うんですよ
わたしも本書から子育てのヒントをもらいました。
今回は、本書の内容ともらったヒントをご紹介です。
- 「モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方」 の内容
- 「モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方」 のポイント
- 「モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方」 からもらった子育てのヒント
- 「モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方」のまとめ
「モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方」 の内容
著者の伊藤美佳さんは、26年間幼稚園・保育園に勤め、現在は乳幼児教室の代表理事をされています。
モンテッソーリ教育とハーバード大学教授の「多重知能理論」を取り入れて、日本人向けにアレンジした「9つの知能」を開発し、教育に取り入れています。
本書「子どもの才能の伸ばし方」 では伊藤さんが開発した「9つの知能」を家庭でできるように40のメソッドとして紹介しています。
モンテッソーリ教育とは
「モンテッソーリ教育」は、将棋の藤井颯太さんが幼稚園時代に受けていたことでも有名ですよね。
本書の内容に入るまえに「モンテッソーリ教育」について簡単に紹介しますね。
モンテッソーリ教育は、医師であり教育家であったマリア・モンテッソーリ博士が考案した教育法です。
「子どもには、自分を育てる力が備わっている」という「自己教育力」の存在がモンテッソーリ教育の前提となっています。
(引用)モンテッソーリ教育について | 公益財団法人 日本モンテッソーリ教育綜合研究所
またモンテッソーリ教育の特徴として「敏感期」という考え方があります。
ある時期に特定の能力(「運動」「感覚」「言語」「秩序」)が発達するという考え方です。
よく小さいうちに音楽を始めると「絶対音感」が身に付くという話を聞いたことがある方もいると思いますが、それと同じ考え方ですね。
ハーバード大学の「多重知能理論」
次に「多重知能理論」について簡単なご紹介です。
「多重知能理論」とは、ハーバード大学のハワード・ガードナー教授が提唱しているもので、人間には8つの知能があるという考えです。長所や短所が個人によって違うように、人によってある知能が高かったり、ある知能が低かったりするという考え方です。
(引用)子どもの才能の伸ばし方 p.55より
人によって国語が得意だったり、算数が得意だったり、音楽が得意だったりと違いますよね。
「8つの知能」を意識することのメリットは、子どもの長所に気付きやすい視点を持てるということ。
「うちの子、会話が遅れてるわ」
と子どものことを周りと比較して、マイナス面ばかり目が生きがちですよね。
でも、これを意識することで「会話は少し遅れているだけで、笑顔でのコミュニケーションや体を動かすことが好きみたい」とプラスの部分にも目を向けやすくなります。
「モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方」 のポイント
本書「子どもの才能の伸ばし方」では、 「モンテッソーリ教育」と「ハーバード大学式」を取り入れた親の関わり方と具体的な40のメソッドが紹介されています。
メソッドでは、「具体的な内容」(例えば「早朝散歩」)と取り組め目安となる「適齢期」が合わせて紹介されています。
少し難しいものだと「ゼロ遊び」のようなゼロの概念を学ぶ遊びも紹介されていて、思わずやってみたくなることが、あなたもきっとあるはず。
個人的には
「英才教育しなきゃ!」
と意気込むよりも
「今日は、子どもと何をして遊ぼうかな?」
というヒントを探すために読み返すように使う方が、無理なく活用できると思いますよ。
繰り返し、読みたい本です!
「モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方」 からもらった子育てのヒント
次に、わたしが本書「子どもの才能の伸ばし方」から貰ったヒントについてご紹介しますね。
人間の脳は否定語を判別できない
モンテッソーリ教育とは直接関係ありませんが、わたしが気に留めているのが
「人間の脳は否定語を判別できない」(本書p.124)という点です。
これは例えば、「走ったらダメ!」と言われた子どもは「ダメ」が残らずに「走る」だけが頭に残って走りたくなってしまうという現象だそうです。
「鶴の恩返し」で覗いてしまうのもこれが原因だった!
走ってほしくない場合には「走ったらダメ」ではなく、「歩こうね」と具体的に何をすれば明確にすると良いそうです。
これは日頃のやり取りで使いやすいテクニックですよね。
子どもに選ばせる
モンテッソーリ教育は「特徴的な教材」に目を奪われがちですが、子どもが集中して物事に取り組み、自分で自分を成長させることを大切にしています。
その中で「子どもが選ぶ」という経験を日常からさせることが大事だそうです。
そのためには親も先入観を捨てたり、親の価値観を押し付けずに子どもを尊重することが大切になります。
男の子は、青色や車の服。
女の子 は、ピンクやお花の服。
ついついそういうイメージを持ってしまいますが、子ども本人が気に入れば、どんな色や模様でも良いですよね。
忙しい時など、ついつい親が今日着る服を用意してしまったり、外食だとお子様ランチを勝手選んでしまいますよね。
ついついやってしまう…反省!
子どもの価値観を認めて、自分で決めていく経験を積んでもらう。
そういう経験がいずれ、自分なりの人生を切り開く自信に繋がるんでしょうね。
「モンテッソーリ教育×ハーバード式 子どもの才能の伸ばし方」のまとめ
「モンテッソーリ教育」の「ハーバード式」どちらも共通する大切なポイントは、「親の関わり方」とその「ベースとなる考え方」です。
目の前の子どもの自主性や価値観を大事にして、伸ばしていく。
そういう具体的なヒントと考え方を教えてもらいました。
気になった方はぜひ、読んでみてくださいね。






