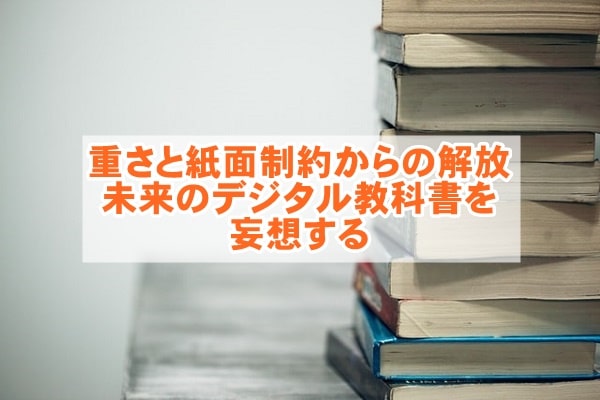
どうも、りょうさかさんです。
2021年5月27日、令和6年度(2024年)からデジタル教科書の本格導入するという目標が文部科学省の報告書の中でまとめられました。
資料の中ではこのようにサラっと書かれています。
令和6年度からのデジタル教科書の本格的な導入を目指すに当たり、児童生徒に対する教育の質を高める上で、紙の教科書との関係をどのようにすべきかについて、全国的な実証研究や関連分野における研究の成果等を踏まえつつ、更には財政負担も考慮しながら、今後詳細に検討する必要がある。(太字・引用者による)
(引用)デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議(第11回)配布資料:文部科学省
そこで部外者のわたしが、未来のデジタル教科書を妄想してみたいと思います。
未来のデジタル教科書とは
最初に書いておきますが、令和6年度のデジタル教科書は紙の教科書と同一内容になります。
これも「デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議」の資料でこのように書かれています。
なお、令和6年度の小学校用教科書の改訂については、教科書の編集・検定・採択をそれぞれ令和3年度、4年度、5年度に行う必要があり、実際には教科書発行者において既に準備が進められている状況にある。これを踏まえれば、検定制度の本格的な見直しについては次々回の検定サイクルを念頭に検討することが適当と考えられ、令和6年度時点においては、デジタル教科書の内容は、紙の教科書の内容と同一であることを維持することが基本と考えられる。
(引用)デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議(第11回)配布資料:文部科学省
しかし、逆に言えば、『検定制度の本格的な見直しについては次々回の検定サイクルを念頭に検討することが適当』という文言からも令和10年度(2028年)の教科書からは紙とデジタル教科書が同一ではなくても良い可能性があるということです。
仮に紙の教科書がなくなるとしたら、色々なことが可能になります。
どんなことができるようになるのか考えてみました。
重さからの解放
紙からデジタルへの大きな変化は、物理的な制約から解放です。
例えば「教科書の重さ」問題も簡単に解決します。
「教科書の重さ」については国会でも取り上げられ、2018年に「置き勉」を認める通知を文部科学省が出しました。
(参考)教科書の重量化問題に関する質問主意書 やっと「置き勉」認め通知 文科省、子供の負担軽減へ | 教育新聞
デジタルになればこの「重さ」問題は解決されて、教科書会社は分量を自由に設定することができます。
例えば「国語」の教科書では、小説や評論の部分抜粋しか掲載されていませんでしたが『全文を読みたい方はここをタップ』とするだけで全文を掲載することが可能になります。
「算数」の教科書なら『「練習問題」「ドリル」「100マス計算」「入試過去問」などの何百ページに及ぶ問題を収録しておいて、使うかどうかは先生、保護者、子どもの判断に委ねます』みたいなことができるわけです。
こういった追加の資料は、社会・理科・英語など、どんな教科でも考えられます。
紙面のページ数や重さなどで掲載できなかった要素を収録することが可能になり、「使う・使わない」を学校や個人の判断に委ねることができます。
特に「練習問題」などが多数収録されることになれば、問題集を買えなかったり塾に通うことのできない家庭への支援に繋がり、「教育の機会均等」の観点からも良いですよね。
一番良いのは、デジタル教科書内にAIが搭載されて、子ども一人一人にあった練習問題などが提示されるとさらに勉強がはかどりますね!
紙面の制約からの解放
紙の教科書は、「本」である以上、目に飛び込んでくるのは「見開きの2ページ」です。
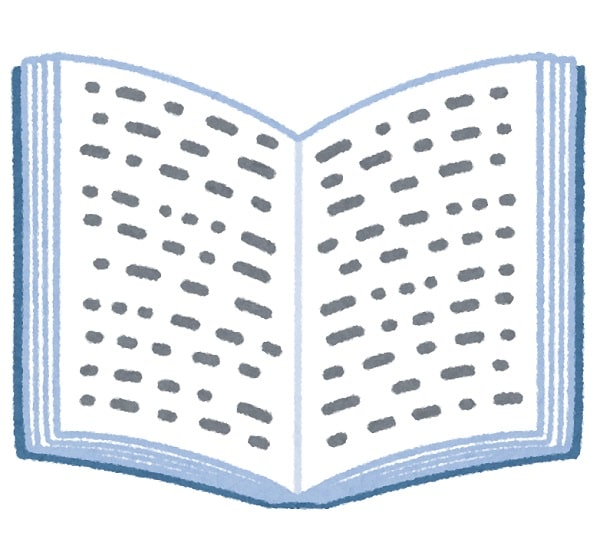
見開きには「全体像が掴みやすい」「今日の授業の範囲がわかりやすい」などのメリットもあるのですが、デメリットもあります。
それは見たくないもの(問題の答えや実験結果)まで見えてしまうことです。
そこで多くの教科書では、次のページをめくらないとわからないように工夫しているそうです。
デジタル教科書なら先生が許可をしないと生徒の端末では表示されないといったことができます。
また「紙の本」ではないデジタルならではの特徴として右開き・左開き、縦書き・横書きといった制約からも解放されます。
例えば「国語」の教科書なら『1章は「左開きの縦書き」の文を読み、2章は「横書き・縦スクロール」の文を読む』といったことが可能になります。
算数の教科書なら「問題毎しか表示されず、学習をしないと次のページを見ることができない」といったことも出来そうです。
動画の授業は当たり前
2028年以降であれば、デジタル教科書内に教科書内容の動画授業が搭載されることは間違いないかなーと思っています。
塾などでは既に授業名人のオンライン授業や動画授業が配信されていますよね。
デジタル教科書内に動画授業が搭載されれば、伝染病による休校、病気や不登校などの状況を問わず、学びを提供することができますよね。
教員の役割は、授業がメインではなくサポート役やファシリテーター役に変わるでしょう。
授業準備の時間も減るので教員の働き方改革に繋がりますし、教員になりたい方が減っていることにも対応できますからね。
あくまで妄想です
以上、こんなことを妄想しました。
今回書いたことは、たぶん教科書より市販の問題集やサービスで先に行われると思いますよ。
「問題毎しか表示されない」というのは既にしているところがありますし。
最短でも2028年の話ですから、実現はまだまだ先です。
実際に恩恵を授かるのは来年2022年に生まれる子ども達以降でしょうね。
それでは、また。





