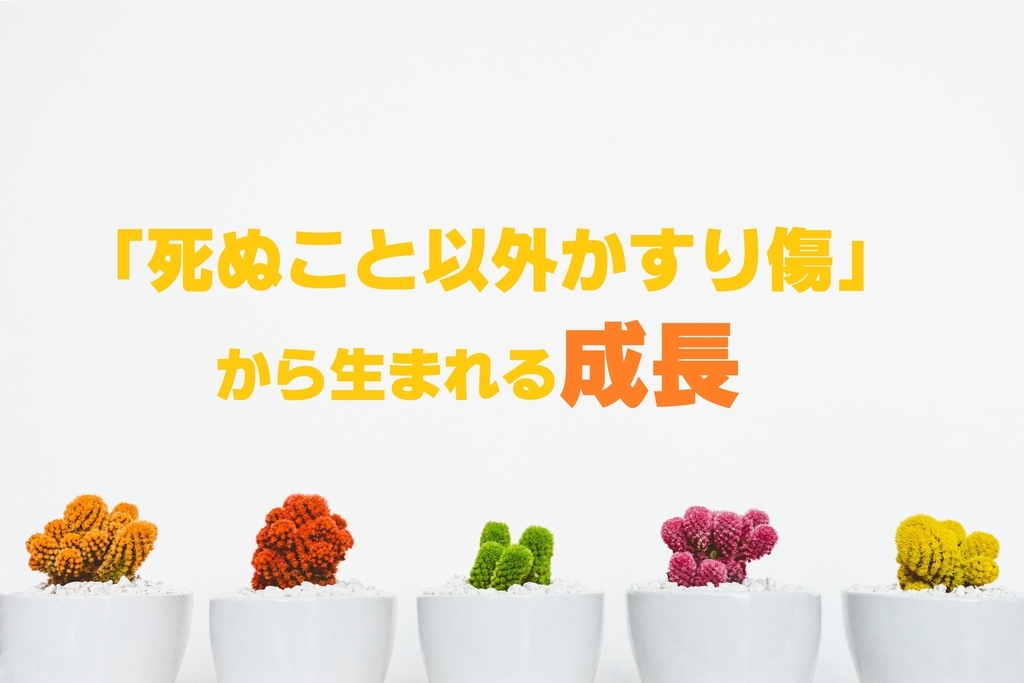
幻冬舎のスーパー編集者・箕輪厚介さんの著書「死ぬこと以外かすり傷」(マガジンハウス)を読みました。
読了まで2時間程度。さらっと読める量になっています。
「死ぬこと以外かすり傷」を読んで「勝ち続ける意志力」という本を思い出しました。そこで感じたことは「成長」についてです。
(Photo by Scott Webb from Pexels)
箕輪厚介さんとは?
1985年生まれ。幻冬舎の編集者。2017年に立ち上げたNewsPicks Bookレーベルの編集長となり担当する書籍は1年間で100万部を突破している。(参考:著者プロフォールより)
わたしには出版社の友人(営業職。幻冬舎ではない)が2人いて、先日、その2人と食事をすることがありました。そのときに話題にあがった1つが箕輪さんのことでした。
編集職ではないということもあってか2人とも箕輪さんには「出版界に新たなスターが現れた!」と好意的でした。
斜陽産業といわれる出版界に日が当たるのであればライバル社であっても喜ばしいことだという捉え方をしているんだと思います。
一方で、興味のない人は全く知らない、というのも事実でしょう。
数々のヒット作を手掛け、箕輪編集室というオンラインサロンを立ち上げたり、水道橋博士とボクシングをしたり、サンデージャポンや東京MXの「五時に夢中」にも出演しているので一般的知名度はあるのかな? と思っていました。
ところが勤めている会社の人に箕輪さんのことを知っているかと尋ねてもほとんど誰も知りませんでした。家族も知らなかった。唯一わたしと同じような嗜好を持つ同期1名だけが知っているという状況。(もちろんサンプルとしては薄弱なんだけどね)
世間の多くはまだまだ彼の存在を知らない。
そんな彼がさらに広く知られるきっかけになる本が「死ぬこと以外かすり傷」はなるんじゃないかと期待しています。
「たった一人の熱狂」とは違う「熱狂」
箕輪さんが編集した幻冬舎の社長・見城徹の「たった一人の熱狂」という本があります。
初めて「たった一人の熱狂」を読んだ時、開いたページの隙間から風が吹き出し顔を容赦なく叩きつけてくるような感覚に襲われながら、必死に目を見開いて読み進めたことを覚えています。
以来、初心に帰りたい時、落ち込んだ時、気合を入れたい時に適当に開いたページから読み返すということをしています。
さて、この「たった一人の熱狂」に出てくるキーフレーズがいくつかあります。
「熱狂」「圧倒的努力」「癒着しろ」「結果が全て」「自己嫌悪、自己検証、自己否定」などなど。
ツィッターなどでも述べられていますし本書の中でも触れられていますが、箕輪さんは編集者として携わった著者のエッセンスを体内に取り入れ、それを自分のものとして表現しています。だから「圧倒的努力」など見城徹語録を見かけることもしばしば。
そういった背景もあり、「死ぬこと以外かすり傷」の目次を読んだ時に「たった一人の熱狂」とどう違うのかな、と気になっていました。
「死ぬこと以外かすり傷」の目次の文言は、「自分の手で稼げ」「恥をかけ、血を流せ」「スピードスピードスピード」「量量量!」「癒着せよ」「熱狂せよ」などなど。
「熱狂」「癒着」なんて言葉はそのまんま。「スピード」「量」という表現も「圧倒的努力」に近い意味合いに受け止めることが出来るし、「血を流せ」などのニュアンスも「たった一人の熱狂」にあるフレーズです。
そう思って読み通した感想は、フレーズで似た表現はあるが受け取った印象は「たった一人の熱狂」とは違う「死ぬこと以外かすり傷」独特のもの。
もちろんビジネス書なので似たような内容もありますが、全て箕輪さんの血肉となった経験から滲み出た言葉に昇華されています。
それもあってか「死ぬこと以外かすり傷」を読んでいると箕輪さんの「熱狂」に飲み込まれてしまい「たった一人の熱狂」と読み比べようという考えは忘れてしまったし、そういう行為自体に興味を持てなくなってしまいました。
だからAmazonなどで目次だけ読んで「うーん、なんとなく内容想像つくなあ」という一部の方(笑)も安心して読んでいただける内容になっていると思います。
それよりも読んでいて思い出したのはプロゲーマーウメハラこと梅原大吾さんの「勝ち続ける意志力」という本のことです。
「勝ち続ける意志力」との違いと共通点
ウメハラさんはギネスにも認定されたプロゲーマー。その著書「勝ち続ける意志力」(小学館)はAmazonの2013年書籍売上1位を獲得しました。
この本の中で梅原さんは「勝ち続ける」ことと「勝つ」ことの違いを丁寧かつ明快に説明し、どうして「勝ち続けること」の方に重点を置くべきなのかを述べられています。
本書の内容をとてもシンプルに表現すると
「目先の「1つの勝利」を追うことは自分の成長を止めてしまう。結果的に勝ち続けることができなくなる。目先の勝負で例え負けたとしても「プロセス」と「成長」を一番大事にする。そうすると結果的に勝ち続けることが出来る」
というもの。(「勝ち続ける意志力」が気になった方はぜひ、一度本書をご覧ください。)
では「死ぬこと以外かすり傷」ではどうなのかというと先ほど紹介した第六章2節のタイトルが「数字から逃げるな」ということもあり数字至上主義、結果至上主義という点では真逆です。
では全て、真逆のような内容かというと、同じようなことが語られている場面もあります。
「変わり続けることをやめない」という節で語られる内容はまさに成長を大事にすること。
特に「おわりに」ではこんな一文があります。
こうして一冊の本を世に出した時点で、今までの僕は死んだも同然だと思っている。(中略)居心地がいいということは挑戦していないということ。成長していないということだ。(p.166より
特徴的なのは箕輪さんが編集者として本を製作する段階は売れる・売れないではなく「読者が読みたいこと」を大事にしている点です。書籍が出来上がり、売る段階から一気にシフトチェンジすることも述べられており、本質的な違いってないんじゃないかと感じました。
ヒーローインタビュー手法の違い
あとウメハラさんも箕輪さんもヒーローインタビューをイメージしていることも共通点です。ただし、二人のアプローチは全然違います。
ウメハラさんの場合
ウメハラさんは、ゲームという社会からまだまだ認められていないものに対して、自分がどれだけ考えて取り組んでいるのか伝える機会を想像して行っていました。
これは自分を客観視したり、言語化したりすることで思考の曖昧さを排除するのに効果的だったように読み取れます。
箕輪さんの場合
対して、箕輪さんのヒーローインタビューは仕事として成果を残すための手法です。
自分へのキャラクター設定、携わっている仕事のストーリー性などを意識するために行っています。
結局、人が金を払うのはストーリーに対して。そのストーリー性の確認と売り込む結果に結び付けるための具体的なプロセスとしてヒーローインタビューまで想定して仕事をしろと語っています。
どちらも根底で共通するのは自己検証という点です。
ヒーローインタビューってポジティブな成功したイメージが必然的に伴いつつ、客観視・言語化・ストーリー性の有無の検証が可能な手法だと考えられるわけです。
これなら今からすぐ取り組むことができますよね。
エールを送る本
「死ぬこと以外かすり傷」は箕輪さん自身の体験と揺さぶられた著者との関わり合いなどを元に構成されています。
熱い言葉が沢山あり「すぐやれ!」「量」「スピード」など読む人達を鼓舞する内容です。
この箕輪さん自身の体験の背景を知りながら、どう人が変わってきたのかを読むのもこの本の楽しみ方の一つだと思います。
あんな凄い人をどう口説いたのか、あの時どんな気分だったのか。鮮やかな結果の裏では、かすり傷とは到底表現できないようなスリリングな背景が描かれます。
またオンラインサロンをする理由となった著者との関わりと住む場所というプライベートな問題は多くの人が共感できるエピソードなのではないでしょうか?
箕輪さんがどう成長し、読者にどう成長して欲しいのか投げかける「死ぬこと以外かすり傷」。
だいたい2時間程度で読める内容です。気になった方は「死ぬこと以外かすり傷」か箕輪さんが編集した「多動力」(堀江貴文)を読んでみるといいと思いますよ。
じゃあ、また。
こんなのも書いています









